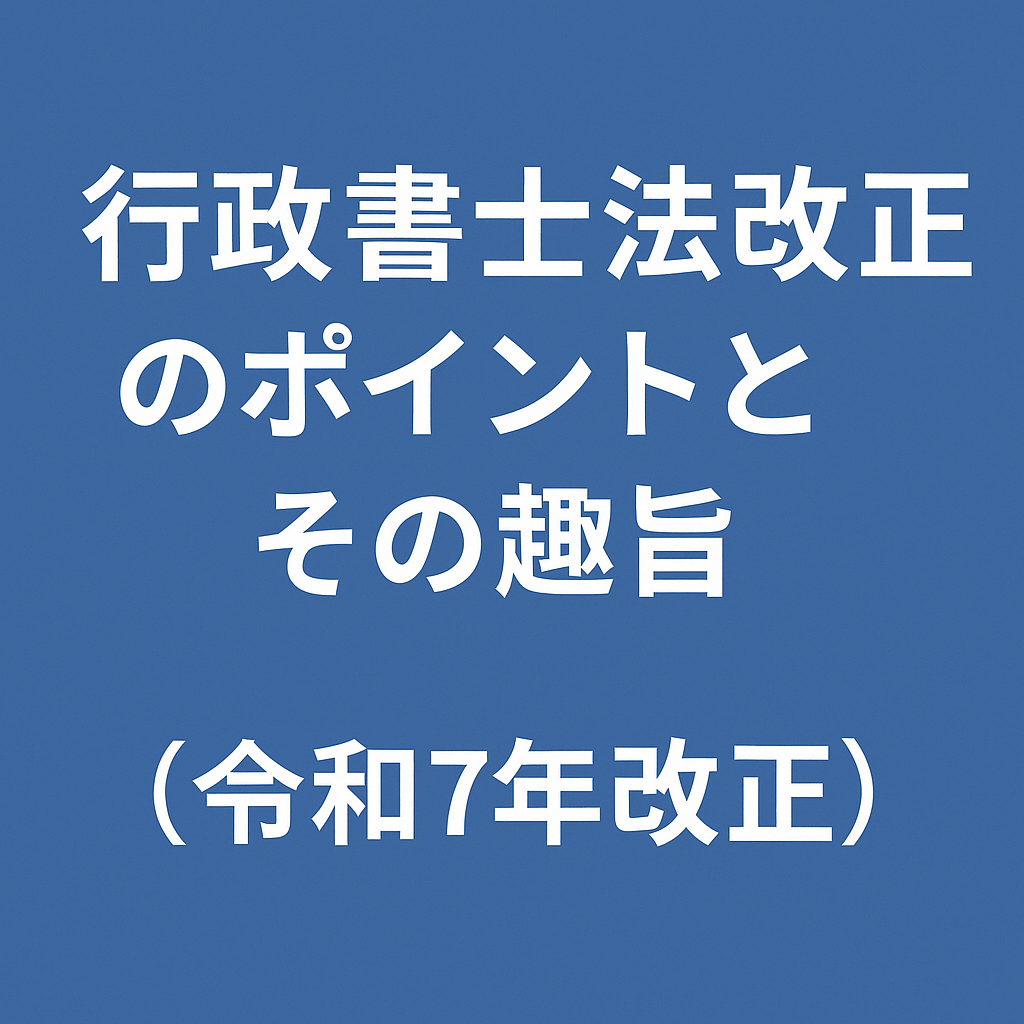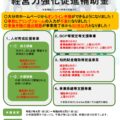行政書士法改正の趣旨
行政書士法改正のポイントとその趣旨(令和7年改正)
令和7年に行われた行政書士法改正は、社会の急速なデジタル化に対応し、行政書士の役割と責任を現代的に再定義する意義のある大改正となりました。本記事では、法改正の主要な5つのポイントについて、その背景や意図も含めて丁寧に解説いたします。行政書士の皆様や関係者にとって、制度を正しく理解し、実務に活かすための参考資料としてご活用ください。
【第1条(使命)の改正】
従来の行政書士法では、行政書士の「目的」が記されていましたが、今回の改正により、これが「使命」として新たに明記されました。これは、弁護士法や司法書士法など他士業の法制度に倣った表現への見直しであり、行政書士の社会的責務が格段に強調されることとなります。「使命」という言葉には、単なる制度の目的を超え、行政手続きの専門家として国民に寄り添い、信頼される職業であるべきとの強いメッセージが込められています。
【第1条の2(職責)の新設】
新設された第1条の2では、行政書士の「職責」について、2項目に分けて明確に規定されました。1項では従来から求められてきた「誠実義務」が法文化され、2項では初めて「デジタル化への対応」が職責として明文化されました。これは、国民が取り残されることなくデジタル行政の恩恵を享受できるよう、行政書士が重要な橋渡し役となるべきであるという国の強い意思を反映しています。特に高齢者や障がい者、ITに不慣れな方々への支援を通じ、行政書士が地域社会の安心を支える役割が明示されました。
【第1条の4第1項第2号(特定行政書士の業務拡大)新設】
特定行政書士が行える業務に関し、これまで制限されていた「関与案件のみ代理可能」という条件が撤廃され、国民自身が申請した案件についても行政不服申立ての代理が可能となりました。これは、今後のデジタル行政において、国民が自らオンライン申請を行うケースの増加が見込まれる中で、審査過程における不許可処分などに対しても専門家による権利救済が機能するようにするための措置です。また、災害復興支援や各種給付金の申請で不許可となった事例にも対応できるよう、行政書士のネットワークを生かした実践的な支援が期待されています。
【第19条第1項(業務制限規定の趣旨明確化)改正】
行政書士の独占業務である書類作成について、従来は「報酬を得ること」が前提であるがゆえに、報酬名目のすり替えによって無資格者が実質的な業務を行うケースが問題となっていました。今回の改正では、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言を追加し、名義貸しや代行行為の排除に向けた明確なメッセージを発信しています。これにより、無資格者による書類作成・相談行為が国民に与えるリスクを抑え、行政手続の専門家としての行政書士の地位がより一層守られることになります。
【第23条の3(両罰規定)の整備】
今回の改正では、法人の関与がある場合の責任を明確にするため、「両罰規定」が新たに整備されました。これは、行政書士法違反行為を無資格者が行った場合、その個人のみならず、関与している法人にも罰則を科すことができるというものです。また、行政書士本人が違法行為を行った場合、その所属する行政書士法人にも同様の責任を問うことができるようになり、コンプライアンス体制の強化が求められています。組織ぐるみの違法行為の抑止と信頼性の向上を図る重要な改正です。
【まとめ】
令和7年の行政書士法改正は、「使命・職責の明確化」「業務範囲の拡大」「無資格者排除の強化」という3本柱を軸に、実質的な5項目の改正がなされた大改正です。これにより、行政書士の社会的責任と専門性が再確認され、国民への支援や救済の実効性も飛躍的に向上することが期待されています。この改正の実現には、多くの関係者の尽力と行政書士会の結束が不可欠でした。今後も国民に信頼される存在として、制度の健全な運用と発展に貢献してまいります。
目次
- 【第1条(使命)の改正】
- 【第1条の2(職責)の新設】
- 【第1条の4第1項第2号(特定行政書士の業務拡大)新設】
- 【第19条第1項(業務制限規定の趣旨明確化)改正】
- 【第23条の3(両罰規定)の整備】
- 【まとめ】
行政書士法改正の背景
2025年7月20日
特定行政書士 御姓啓二